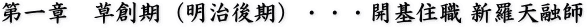 |
 |
| ◆天融寺のはじまりと恵庭の開拓 |
◆天融寺の開教年はいつであったのか
|
漁村に始めて布教に来た僧は、等木樹教か等力利教か/本堂新築落成は、明治28年か明治40年か?
千歳山天融寺と公称したのはいつからか?/伝承「大谷派説教場ヲ創立」と記述「天融寺の濫觴」を読み解く
開基住職新羅天融師が来村する |
|
| ◆説教場の創立 |
| ◆開拓端緒期と天融寺 |
| ◆寺号公称への胎動 |
| ◆一寺創立を果たした新羅天融師 |
◆本堂新築への動き
|
本堂新築寄付金奉加帳/寺号公称出願の経緯/但書を推論する/発願者の六名は誰か
・・・・・一枚の写真・・・・・
古い本堂(建物)と見做した場合/新築の本堂と見做した場合/服装からして4月早春か・あるいは秋かー。 |
|
| ◆本堂、庫裡の新築、落成 |
| ◆御本尊、阿弥陀如来立像の請来 |
| ◆田中文弥文書 |
| ◆本山相続講胆振国第一小会の結成 |
| ◆御影の出願と下付 |
| ◆御法義相続の基礎としての講組織 |
| ◆天融師とお講の結成 |
| ◆新羅天融師の命終と住職不在期 |
| ○《補記》東大音師と佐々木智龍師/現如上人の北海道開拓と三人の山形の青年僧 |
 |
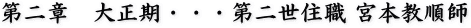 |
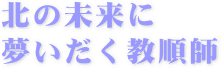 |
◆宮本教順師が天融寺に入寺する
|
教順師の出身寺、内灘村室の宮暁山明證寺を訪ねる/教順師の来歴
・・・・・写真探訪・・・・・
2枚の写真と教順師の役割/天融寺所蔵の写真が札幌刑務所にも保存されていた事実は何を物語るのか |
|
| ◆婦人法話会漁支部が発足する |
◆教順師の筆になる御膳水の碑
|
・・・・・境内探訪・・・・・
最初の梵鐘と鐘楼堂/開基住職の墓碑建立 |
|
| ◆定例法座の再開と拡充 |
| ◆教順師と御講の結成 |
| ◆恵庭村最初の無声映画 |
◆聖徳太子二歳尊像招来する
|
現在、当寺には次のような聖徳太子御尊像の縁起が伝わっている/天融寺の太子像は富山県瑞泉寺の分身 |
|
◆天融寺大正邂逅記
|
大正 4年 札幌別院宗祖聖人六百五十回御遠忌へ参勤
大正 6年 盤尻十日講/宮殿、復弥壇の新調/胆振国視察に任命される
大正 7年 最古の境内地測量図と境内地の拡張
大正 8年 最初の座敷が建つ/龍音師の結婚
大正11年 布教使としての教順師/聖徳太子の奉讃法要、厳如上人二十七回忌、開基住職十三回忌法要厳修
大正12年 第二世坊守の命終
大正13年 中尊前前卓の新調
大正14年 大谷派北海教区商議会一級議員当選
大正15年 婦人法話会漁支部会員名
昭和 2年 第二世住職の命終 |
|
 |
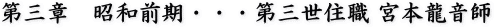 |
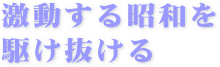 |
| ◆龍音師、第三世住職に就任する |
| ◆北海教区商議会議員となる |
| ◆現鐘楼堂を建築する |
| ◆前住職一周忌、三回忌法要、大正天皇奉悼法要 |
| ◆龍音師病む |
| ◆昭和5年頃の北海道教区における天融寺 |
| ◆庫裡の改築 |
| ◆本堂改築と寺地移転の問題 |
| ◆満州事変、上海事変と戦病死者追悼法要 |
◆うち続く凶作と本山慰問
|
◆精力的な教化活動
|
天融寺日曜学校/青年信仰夜話会/青年団布教、在家布教の実施 |
|
| ◆婦人法話会名誉顧問大谷喬子様のご来寺 |
| ◆境内地に桜、松の植樹 |
| ◆開基住職二十三回忌、第二世住職七回忌法要、並びに開基当時功労者追弔会勤修 |
| ◆新発意の得度と大谷中学校入学 |
| ◆第四組組長に就任 |
| ◆天皇陛下奉迎の婦人法話会漁支部会員 |
◆本堂再建(改築)の大事業
|
総会で本堂再建を決議する/本堂再建への強いおもい―募金を開始する/設計図面の依頼/道庁への出願/
寄附募集願/「天融寺本堂再建趣意書」と恵庭村および当村周辺市町村への募金開始 |
|
| ◆日華事変勃発と国家総動員法公布 |
◆寄付金募集延期願を北海道庁長官へ提出する
|
厳しい寄付金の募集活動/小清水氏と工事契約を結ぶ/帝室林野局より本堂用材の払下げを受ける |
|
◆本堂改築工事の経過
|
解体と地搗/大工の棟梁と設計棟梁/工事既成部分検定を実施/追加工事の発生/御内陣欄間巻障子の寄進 |
|
| ◆本堂竣功と道庁への届出 |
| ◆気仙大工 花輪喜久蔵 |
| ◆法務員寶喜諒師の出征と戦死、日中戦争戦死者の村葬 |
| ◆千歳市街説教場創立掛申付けられる |
| ◆昭和15年頃の葬儀 |
| ◆御仏事としての本堂再建 |
| ◆龍音師と庭木、中庭 |
| ◆戦前戦後の頃の当寺の伽藍配置 |
| ◆東札幌説教場創立 |
| ◆新発意の大谷大学入学 |
| ◆北海道教区第四組追弔会 |
| ◆宗教団体法の制定 |
| ◆開基住職三十三回忌法要厳修 |
| ◆龍音師と御講 |
◆龍音師の命終
|
| ○《補記》戦前、教順師・龍音師の代に天融寺の法務を手伝われた方々 |
 |
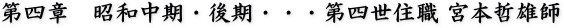 |
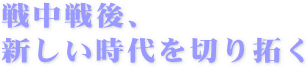 |
| ◆哲雄師第四世住職就任 |
| ◆役僧を尋ねる |
| ◆梵鐘、仏具を供出する |
| ◆月忌参りを祥月参りに |
| ◆三世坊守宮本そのい教師資格取得 |
| ◆第二世、第三世の法要勤修 |
| ◆宮本哲雄師 結婚する |
| ◆戦時下の天融寺 |
| ◆防空壕掘りと御本尊の避難 |
| ◆哲雄師、北海道大谷派の挺身隊に参加 |
| ◆北海高等女学校生の長期援農宿泊 |
| ◆敗戦の日玉音放送に聞き入る |
| ◆終戦前後の報恩講 |
| ◆松園国民学校の焼失と天融寺仮教室 |
| ◆役僧川田由太郎氏の葬儀 |
| ◆第四世住職嗣子の葬儀 |
| ◆哲雄師の代における戦没者追悼(弔)会 |
| ◆戦後天融寺の法務を手伝われた方々 |
◆戦後の布教教化活動
|
和敬仏教青年会発足する/文化思想講座の開催/戦中、戦後の青年団布教/和敬日曜学校の開校/
在家布教の展開 |
|
| ◆天融寺基本財産の推移 |
| ◆寺の山林から立木を切り出し、薪をつくる |
| ◆第三世住職七回忌、第二世坊守二十五回忌 |
| ◆第四世住職嗣子三回忌ならびに門徒功労者追悼会厳修 |
| ◆役僧住宅の建設 |
| ◆天融寺蓮如上人四百五十回御遠忌法要とその記念事業への取り組み |
| ◆梵鐘の新鋳招来と慶讃法要 |
| ◆蓮如上人四百五十回御遠忌法要ならびに第二世住職二十三回忌、宮本正暁氏二十五回忌法要厳修 |
| ◆本堂屋根のトタン葺工事が完成 |
| ◆北海道開教八十年記念法要で新羅天融師表彰 |
| ◆第四世住職の発病と治療 |
| ◆天融寺門徒会の結成 |
| ◆宗教団体法と宗教法人法 |
| ◆本堂と庫裡の電気関係設備を充実させたころ |
| ◆前住職、前々住職、前坊守の御法要勤修 |
| ◆火防用井戸の設置 |
| ◆有線放送への加入 |
| ◆オートバイの購入 |
| ◆新門様の北海道冷害御慰問 |
| ◆レンガ造門柱の寄進 |
| ◆坊守、若院の得度 |
| ◆乗用車ダットサンの購入 |
| ◆納骨堂の建立 |
| ◆納骨堂の落成法要、落成式、祝賀会 |
| ◆大谷婦人会創立五十周年記念式典挙行 |
| ◆開基住職五十回忌法要勤修 |
| ◆親鸞聖人七百回御遠忌法要の厳修 |
◆天融寺の宗祖聖人七百回御遠忌を厳修する
|
記念事業として座敷の改築を計画/本堂屋根葺工事と水道・消火栓の取付工事/総代の選出方法が選挙から地区の推薦へと変わる/納骨堂地下内部仕上工事と地下納骨壇の増設 |
|
| ◆庫裡、会館の建設 |
| ◆天融寺前の道路舗装工事竣工 |
| ◆親鸞聖人御誕生八百年 立教開宗七百五十年慶讃法要 |
| ◆屋内消火栓改造工事施工 |
| ◆第三世住職三十三回忌法要勤修 |
| ◆車庫兼物置、外便所等の建設 |
| ◆住職後継者、宮本正尊の結婚 |
◆ボーイスカウトと天融寺
|
恵庭のボーイスカウト生みの親、哲雄師/恵庭第一団の主な動き/本道のボーイスカウトの発展に尽くす/
スカウト精神に生きた哲雄師 |
|
| ◆少年院での宗教教誨と篤志面接活動 |
| ◆若妻会の開催 |
◆日曜学校を再開する
|
少年期、仏様の教えに触れることを大切にしたい/ふたたび開講式を行う/大谷キャラバンと若い芽の伸びる会/
全道を駆け巡った第十七次・十九次隊/真宗に学ぶ会の発足 |
|
◆檀信徒、参詣の足
|
檀信徒はどのようにしてお詣りしたか/漁川を渡ってのお詣り/国鉄バス「天融寺前」停車場
法座の開始時刻が10時に変更される |
|
 |
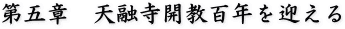 |
| ◆風雪百年、輝く未来 |
◆本願寺街道開削一世紀
|
北海道開教百年を記念する/現如上人遺徳顕彰委員会設立/現如上人銅像建設
現如上人(東本願寺)北海道開教百年記念法要/北海道開教百年記念式典 |
|
◆天融寺開教百年法要へ向けて本堂修復事業に着手
|
百年法要へ向けた本格的な整備の願い/本堂を修復した寺院を視察する/本堂修復工事の設計を依頼
基本方針が門徒の総意で固まる/皆で募金協力を広げていく/大屋根の本堂へ |
|
| ◆本堂修復落慶法要、落慶祝賀会の実施 |
◆天融寺開教百年を迎える
|
慶讃法要と記念事業/趣意書の作成と募財の実施/記念計画作成の際出てきた二つの問題/募金の開始と記念事業の進展/御連枝を御招待することに決まる/追加事業の実施/法要日程の詳細を決める |
|
◆開教百年慶讃法要庭儀(慶讃パレード)
|
カラッと晴れた七月の青空、開闢以来の大庭儀となる/開教百年慶讃法要結願日中の参勤御法中 |
|
| ◆門徒功労者表彰式 |
| ◆寄せられた特志寄付 |
| ◆開教百年慶讃祝賀会 |
| ◆教区・組への記念志納と隣接境内地の取得 |
| ◆法要の決算を報告する |
| ◆天融寺のあゆみと寺格 |
| ◆第三世坊守の命終 |
| ◆天融寺千歳支院の開設 |
| ◆龍音寺の寺号公称、一寺創立 |
| ◆天融寺勤行練習会および正信偈・歎異抄講話の実施 |
| ◆恵庭バイパス事業の着工と境内地の買収 |
| ◆候補衆徒(若院)の嗣子並びに准坊守の得度 |
| ◆第四世住職、藍綬褒章を受章 |
| ◆公共下水道の利用が可能となる |
| ◆宮本正尊候補衆徒、責任役員に就任 |
◆総代定数の変更
|
・・・・・第三世坊守の生涯・・宮本そのい・・・・・ |
|
 |
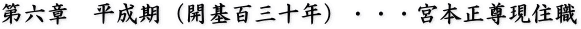 |
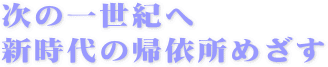 |
| ◆哲雄師の意志表示と正尊候補衆徒の本山住職修習 |
| ◆第四世住職の発症 |
| ◆総代帯同の研修と住職任命式 |
| ◆第五世住職襲職(継承)法要、第三世住職五十回忌法要 |
| ◆天融寺納骨棚使用上の内規の制定 |
◆新納骨堂の建立に着手する
|
建設委員会の発足/納骨堂視察研修旅行の実施/「新納骨堂建設計画の概要」案の策定/「新納骨堂建立趣意書」の作成と納骨壇募集の開始/総代の改選と新たな「新納骨堂(新座敷)建設委員」の選出/本設計を依頼/開発行為が許可される/業者の決定と納骨堂建物の完成/納骨堂御本尊、仏間仏具の発注を行う |
|
| ◆無量寿堂とインドのチャイティヤ窟 |
◆本山における蓮如上人五百回御遠忌法要
|
御遠忌勧募のお願い/御遠忌テーマの発表/御遠忌団体参拝の実施 |
|
◆新座敷を建設する
|
| ◆確認申請提出へ向けての準備 |
◆蓮如上人五百回御遠忌法要、新納骨堂・新座敷落慶法要厳修
|
新納骨堂建設工事特別会計決算書/新座敷建設工事会計決算報告/本堂参詣の間に椅子を導入/中庭の造成/本堂南面妻壁修復工事の実施/宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌・真宗本廟両堂等御修復懇志金のお願い |
|
◆天融寺清田支院顯浄寺の開設と寺号公称
|
◆聞法会館・納骨堂・庫裡の建設に向けて
|
三点の検討課題/検討の経緯/総代改選と新たな検討委員会の発足/建設計画概要の策定/建設委員会の発足と建物の完成へ向けて・会館が「光照殿」と命名された理由 |
|
◆新納骨堂第二無量寿堂の建立
|
| ◆宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要団体参拝 |
◆落慶法要を計画する
|
◆天融寺宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要
併修、会館・納骨堂・庫裡落慶法要 開基住職百回忌法要 平成二十四年度報恩講
併催、大谷婦人会天融寺支部創立百周年記念大会
|
初逮夜法要(大谷婦人会天融寺支部百ヶ年間物故会員追弔法要併修)/御門首による帰敬式/庭儀/記念写真/天融寺宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要、会館・納骨堂・庫裡落慶法要・開基住職百回忌法要/記念式典/表彰状、感謝状の贈呈/慶讃祝賀会/決算報告 |
|
| ◆若院、博士の学位を取得 |
| ◆本堂内陣に防犯カメラを設置 |
| ◆第四世住職 宮本哲雄師の葬儀 |
◆第五世住職の布教強化活動
|
宗門の教化事業にご門徒と共に積極的に参加/天融寺真宗入門講座と同朋会推進員教習/第二回真宗入門講座(同朋会推進員前期教習)を開催/後期講習の実施/天融寺「親鸞講座」の開催/宗門外での教化伝道活動 |
|
| ◆昭和五十年代以降、天融寺の法務を手伝われた方々 |
◆仏跡巡拝の旅
|
初めてのインド/混沌と雑踏の中から見えてきたもの/インドでの行程 |
|
◆第一回インド仏跡巡拝の旅
|
◆中国仏教遺跡巡拝とシルクロードの旅
|
中国西域に仏教東漸の道を訪ねて/敦煌、西安、山西省 |
|
◆第二回インド仏跡巡拝の旅
|
| ◆ヨーロッパの世界遺産を巡る旅 |
| ◆天融寺大谷婦人会主催ハワイ東本願寺別院参詣の旅 |
| ◆天融寺のこれから―未来への継承― |
 |
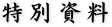 |
◆天融寺における布教・法座の歩み
|
戦前・戦中・戦後における布教・法座のあゆみ/布教・法座の年間開催日数/定例布教(法座)
報恩講/彼岸会/修正会(元旦慶讃法要) |
|
◆大谷婦人会天融寺支部の歩み
|
大谷婦人会の呼称の変遷/会の目的/天融寺支部の歩み/大谷婦人会天融寺支部創立百周年記念大会/
未来への新たな出発/宮本春美大谷婦人会天融寺支部長の活躍 |
|
| ◆天融寺の旅行記 |
◆阿弥陀如来立像
|
阿弥陀如来立像とともに歩んだ天融寺の歴史/阿弥陀如来立像/
《寄稿》天融寺所蔵阿弥陀如来立像並びに胎内納入文書について |
|
| ◆あとがき |
| ◆編集後記 |
 |
|
 |
 |
■歴代住職・坊守名簿
■歴代責任役員名簿
■歴代総代名簿
■歴代護持委員名簿
■歴代世話方名簿
■天融寺門徒会 歴代会長、副会長、監事名簿
■大谷婦人会天融寺支部歴代役員
■歴代特志寄付者
■歴代顕彰者
■天融寺年表
■天融寺所蔵資料目録
■天融寺所蔵雑誌目録 |
|